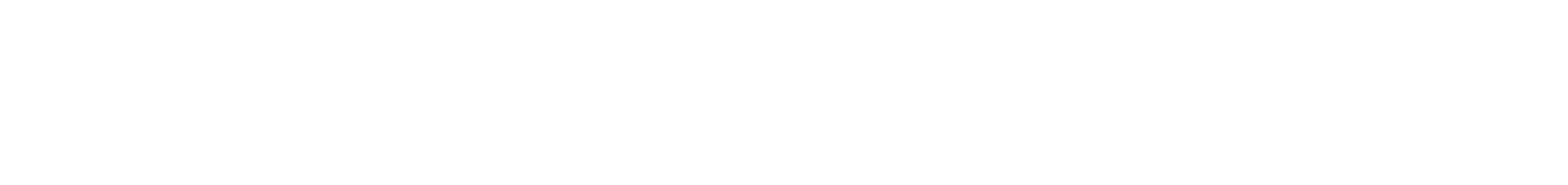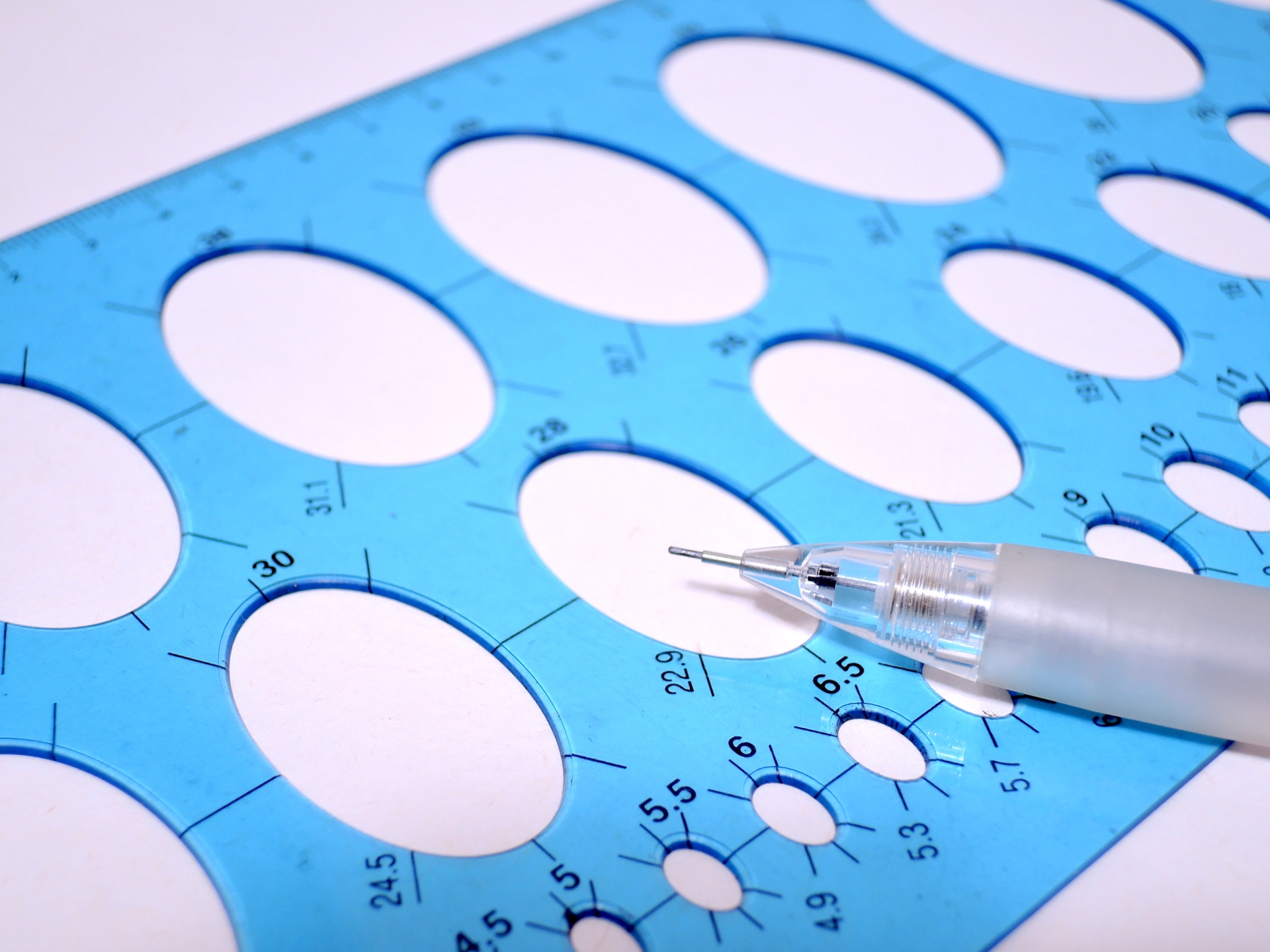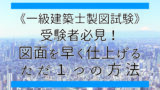建築技術研究所 です。
ブログやX (Twitter)から建築士試験についてお伝えしています。
特に、製図試験のポイントや考え方について自身の受験経験を基に記事を作成しています。
試験に向けての学習の補助として活用していただけると嬉しいです。
今回は、製図試験で課題を解いていくうえで大切なことについてお伝えしたいと思います。
結論これ言えば、一級建築士 製図試験に重要なスキルは、【課題文の読取】【時間管理】【作業後の確認】の3つです。
今回は、これらについて考えます。
【文章の読取】
まずは、文章の読取です。
建築士として、条文を適切に理解するためにも適切な読解力が必要になります。
試験的な読取の詳細な内容は、別記事でご紹介したいと思いますが、今回は特に重要なポイントをお伝えします。
設計条件
試験での施主の要求です。読み落とすと大きな減点につながります。
特に、複数回、同じ内容の記述がある場合は重要度が高く、その要求の欠落は合否に直結するので注意しましょう。
面積
建築物の床面積、建蔽率・容積率については、不適合=不合格です。
正しく読取りができていないと「思い込み」の原因になります。何度も手を動かして確認しましょう。
要求室の面積も建物全体の面積を検討するためには必要です。
床面積「適宜」で出題されるケースも増えているので、利用者の人数や用途を正しく読取り、適切な面積を計画しましょう。
動線
要求室間での動線や室と屋外施設の動線、管理ゾーンからの搬入動線は、課題文から正しく読取りましょう。
動線についての内容は、試験の重要な採点ポイントのひとつですが、同時に、問題を簡単に解くためのヒントでもあります。
動線の要求が多い課題ほど、難易度が低いです。
【時間管理】
次に、時間管理です。
試験時間(6時間30分)の使い方は、合否を分けるポイントのひとつです。適正に時間を配分することで、不合格になる確率を減らすことができます。
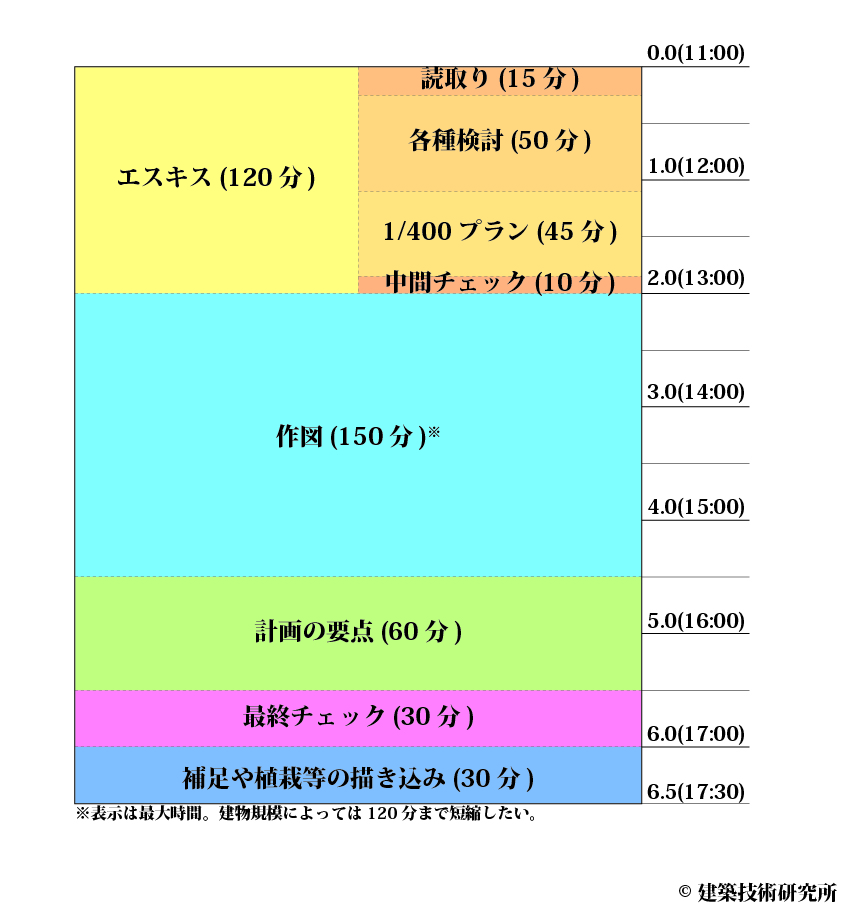
下図は、私が目安とする時間配分です。
エスキスは、2時間を目安にしていました。
どんなに難しいと思う課題でも2時間半を超えてはいけません。理由は、最終的な結果として、2時間半でできたプランと3時間使ったプランに大きな差はでなないからです。
作図の目安は、2時間半です。(補足や植栽等の描き込みを除く)
内容によっては、2時間を目指したいところです。
作図は、3時間を超えてはいけません。
この試験に勝つためには、後半にいかに時間を残す必要があります。
作図スピードは単に練習の結果なので、できるまで練習するようにしましょう。
作図スピードに関しては、早いうちに上げておきましょう。
学科からの人は、学科試験終了(7月中旬)から1か月(8月中旬)くらい、2,3年目の人は、3月から勉強を始めて、遅くとも4月中には、安定したスピードで書けるようになっておく必要があります。
計画の要点は、最低でも1時間は使いたいです。
経験上、最低でも1時間は使わないと合格レベルの内容を書き切れません。
図面と比べて、ないがしろにされやすい計画の要点ですが、図面で差が付かないと合否に影響するため、エスキスや作図で短縮できた時間は、この計画の要点に使いたいところです。
最終のチェックは、計画の要点と同様にできる限り時間を使いましょう。
そのためにも、試験前半で時間を短縮する必要があります。
最後に時間の限り、補足や植栽等の描き込みをしていきます。
補足は最低でも各図面1つ以上は、入れていきましょう。
特に課題文の「Ⅰ.設計条件」に書かれている内容や動線計画について書くと効果的です。
【作業後の確認】
続いては、作業後の確認(中間・最終チェック)です。
各工程でチェックすることは、この試験において最も重要です。どんなに優れた計画だったとしても、作図中の不備は必ずあるので、優先順位を決めてひとつずつ潰していきましょう。
《中間チェック》
チェックのタイミングは、各種検討終了後とプラン終了後です。
計画段階での面積チェックは、間違いがないように繰り返しましょう。
各種検討終了後
プランに移る前に、各種検討で算出した面積が、与条件に適合しているかを確認します。
もし、そこで過不足があれば、プランに移らず、もう一度検討し直さなくてはいけません。
また、各種検討中に斜線制限についても検討するかと思いますが、間違っていないかをもう一度確認しましょう。
プラン終了後
プラン終了後にもう一度、面積を確認しましょう。
特に、プラン中にスパン割を変更した場合、思いがけず面積が増えている時があるので注意が必要です。
また、要求室・その他の施設が決められた数、面積であるかを確認しましょう。
特に、室数の不足は、要求に対する重大な不整合でランクⅣになってしまう可能性があります。
その他
要求室については、プラン終了後のチャックも必要ですが、確実に進めていくためには、プラン中に課題文をチェックしながら進めることが重要です。
この試験において「思い込み」が重大なミスにつながります。自分の記憶力を過信せず、常に課題文を確認するように心がけましょう。
《最終チェック》
最終チェックは、優先順位を決めてチェックしていきましょう。
まずは、以下の項目から確認していきます。
・面積(建蔽率・容積率)
・高さ(斜線制限)
・防火区画
・避難距離
その後に要求室の条件が適合しているかを確認していきます。
要求室の面積や人数指定も大切ですが、作図中の室名間違いには、室の欠落となってしまう可能性があるので、特に注意しましょう。
まとめ
- 文章の読取は、思い込みをせず、課題の要求を正確に理解する
- エスキスは時間厳守
- チェックは、優先順位を決めて行う