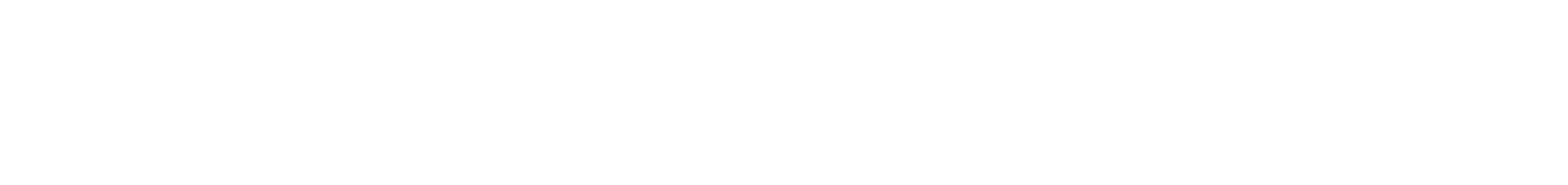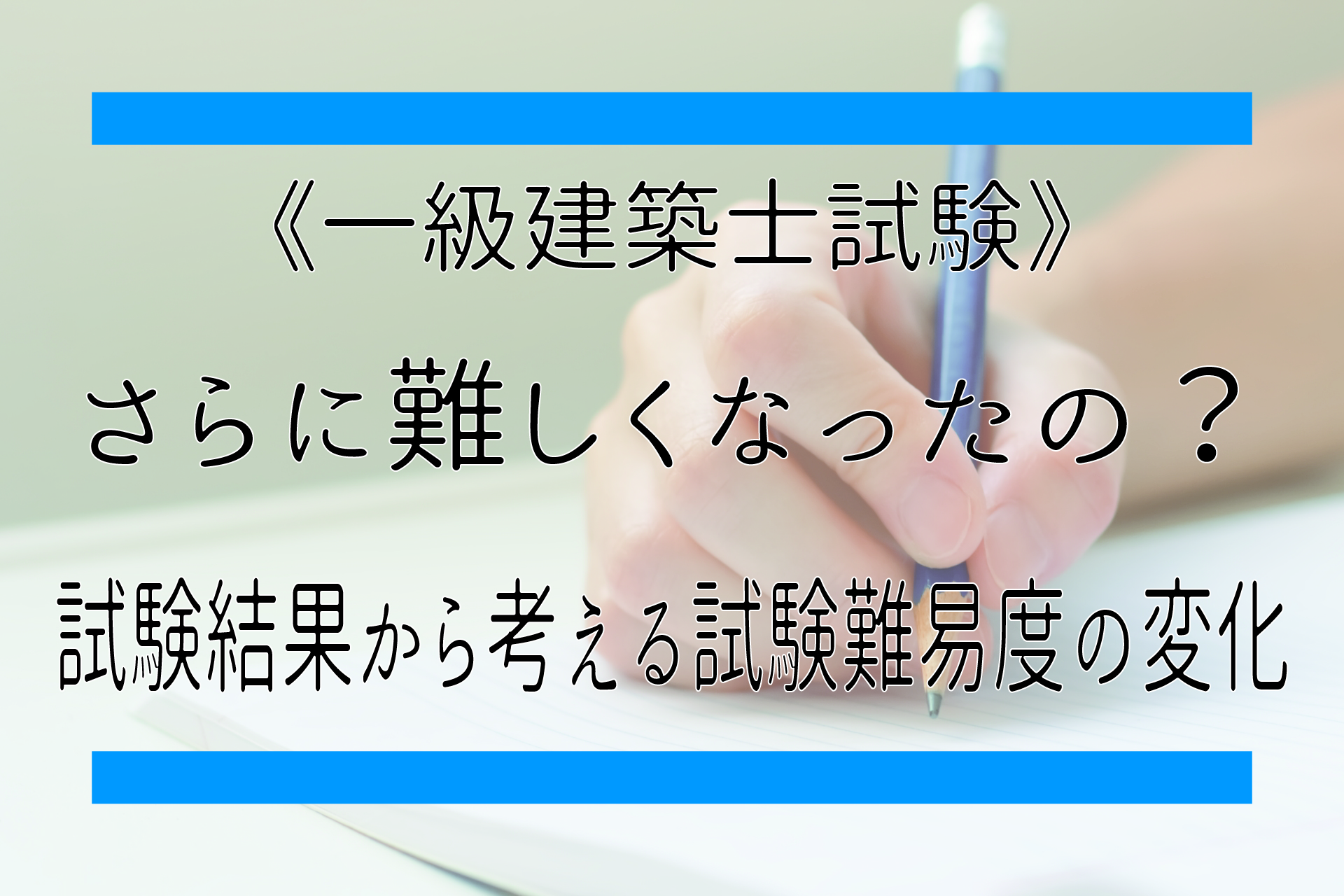建築技術研究所 では、ブログやTwitterから建築士試験についてお伝えしています。
特に、製図試験のポイントや考え方について自身の受験経験を基に記事を作成しています。
試験に向けての学習の補助として活用していただけると嬉しいです。
建築士試験は、時代に合わせて少しずつ変化しています。
試験合格には、その変化に応じて戦い方を変える必要があります。
そこで今回は、試験結果(統計)から考える試験難易度の変化についてまとめました。
直近の試験結果
平成20年度から令和4年度の結果を見てみます。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| H20 | 51,323 | 4,144 | 8.1% |
| H21 | 46,942 | 5,464 | 11.6% |
| H22 | 43,520 | 4,476 | 10.3% |
| H23 | 39,020 | 4,560 | 11.7% |
| H24 | 34,511 | 4,276 | 12.4% |
| H25 | 31,704 | 4,014 | 12.7% |
| H26 | 30,330 | 3,825 | 12.6% |
| H27 | 30,462 | 3,774 | 12.4% |
| H28 | 30,648 | 3,673 | 12.0% |
| H29 | 31,061 | 3,365 | 10.8% |
| H30 | 30,545 | 3,827 | 12.5% |
| R1 | 29,741 | 3,571 | 12.0% |
| R2 | 35,783 | 3,796 | 10.6% |
| R3 | 37,907 | 3,765 | 9.9% |
| R4 | 35,052 | 3,473 | 9.9% |
| R5 | 34,479 | 3,401 | 9.9% |
令和5年度の試験は、総合合格率【9.9%】となり、令和3年度以降の試験では10%を割っています。
試験は難しくなったのか
受験資格が見直される前は約12%で推移していましたが、近年は、合格率が1桁台にまで下がりました。
結果だけ見れば、試験が難しくなったように感じますが、ほんとうにそうなのかを合格率が下がった理由とともに考えていきます。
建築士法改正
建築士試験を受験される皆様であれば、ご存じの方も多いと思いますが、令和2年度の試験から受験資格の見直しをはじめとする建築士法の改正が行われました。
ここでは、具体的な内容には触れませんが、簡潔にお伝えすれば、これまでの「受験資格」が「免許登録要件」となり、これまでよりも早く試験を受けることが可能になりました。
この改正の背景のひとつには、受験者数の減少があります。
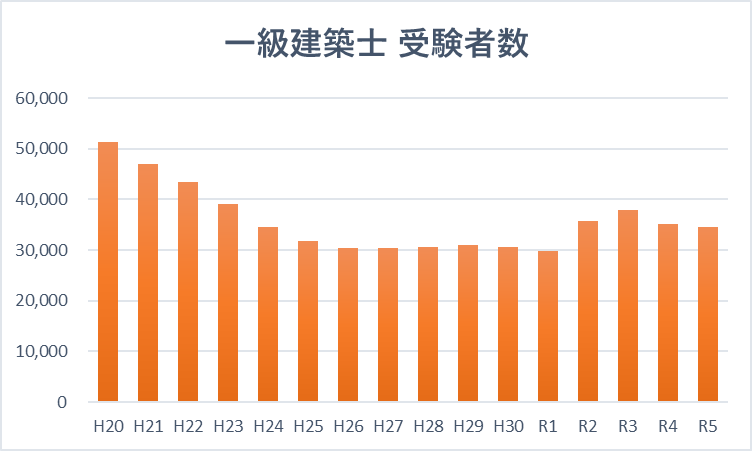
平成20年度からH26年度までの間で減少を続け、それ以降、令和元年度までは横ばいで推移し、旧制度最終年度となる令和元年度では平成20年度の約6割に落ち込んでいました。
そして、この改正の結果として、受験者数は、3万5千人程度となり、改正前5年間と比較すると、5千人程度の増加となっています。
受験資格を見直した要因としては、実務経験の要件を満たす前に他業種へ移る若年層が一定数いることが大きいと思います。試験にさえ合格していれば、業界に残りやすく、転職もしやすくなります。
合格者数の推移
次に合格者数の推移について見ていきます。
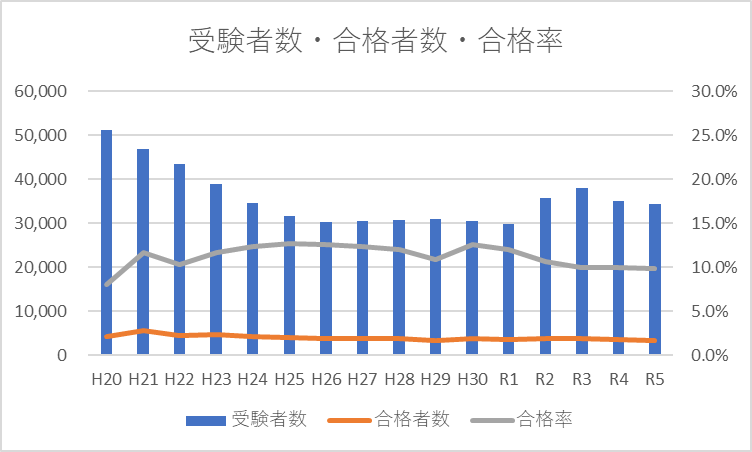
合格者数は、受験者数が30,000人台となった平成26年度の合格者から今まで大きく変わらず、制度改正によって受験者数が増えた令和2年度以降も同様です。
受験者数が増えても合格者数が横ばいなのは、受験資格を緩和し、受験者数を増やしたところで、合格率を変えない(=合格者数を増やす)と、これまでの試験では知識が合格に達してない人を一定数合格させることになり、「建築士」の質(「建築士」の価値)の低下が懸念されるからだと思います。
また、受験資格が緩和されたことで、令和元年以前に比べて、記念受験が増えているようにも思います。
試験難易度
これらから考えると、受験者数(母数)が大きくなっているため合格率は低くなっていますが、今まで以上に身構える程難しくなっているわけではなく、製図試験では、基本となる3つのことさえ確実に身に付ければ、合格する可能性はとても高いと言えるのでな無いでしょうか。
だだし、その質を高めていかなければいけないのも事実です。
製図試験で基本となる3つのことについては、過去の記事をご覧ください。
まとめ
令和5年度の合格率は【9.9%】
合格率低下の要因は、
・制度改正による受験数増加
・制度改正前と同様の合格者数
∴必要以上に身構える必要はなく、これまで通りの対策で合格は可能
ただし、その質は高める必要がある。