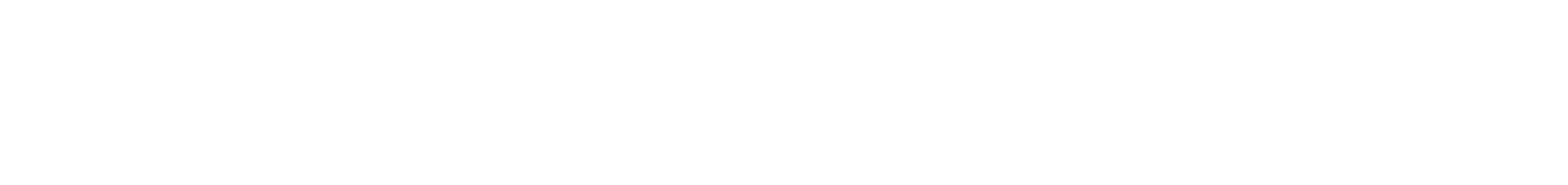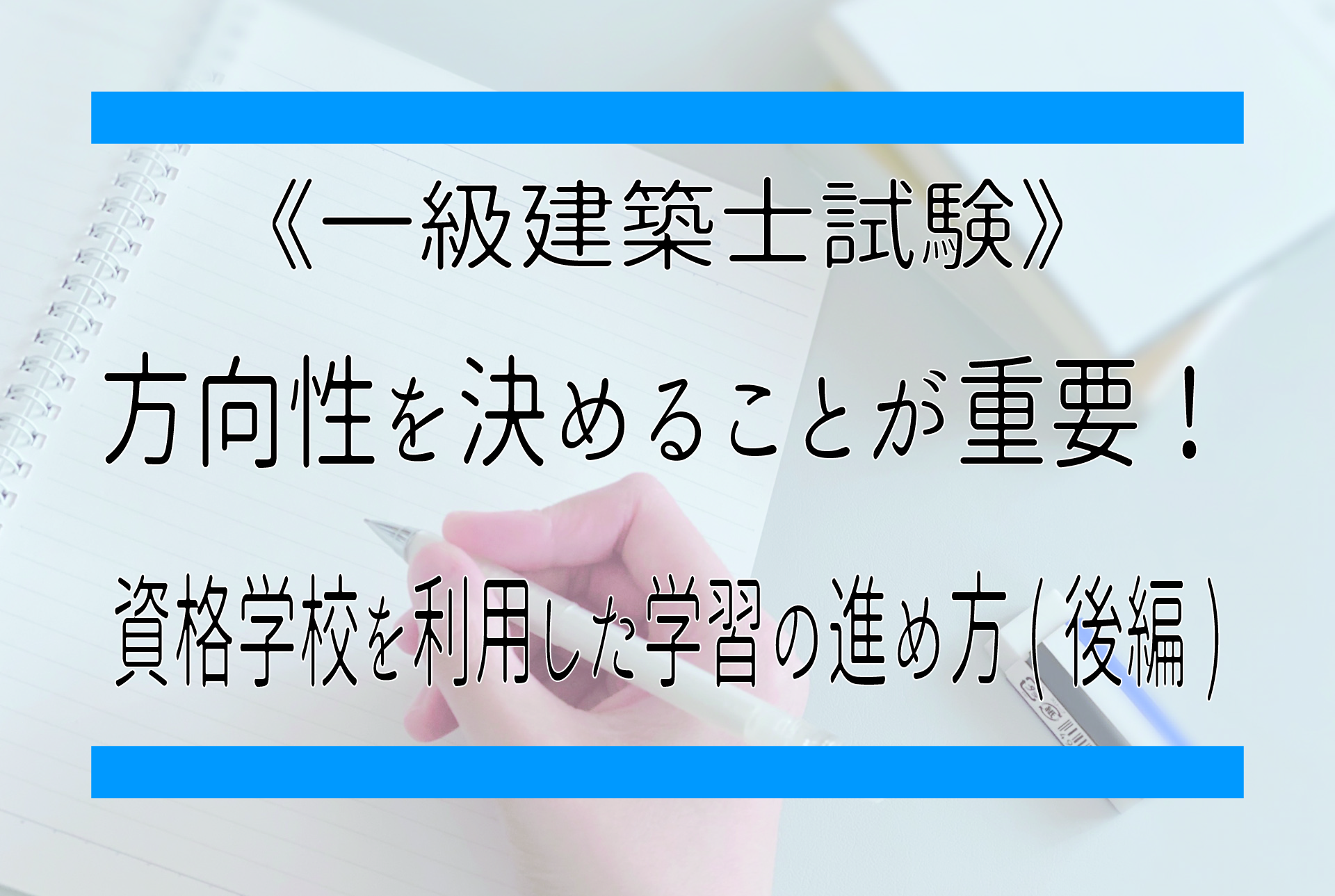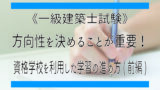建築技術研究所 です。
ブログやTwitterから建築士試験についてお伝えしています。
試験のポイントや考え方について自身の受験経験を基に記事を作成しています。
試験に向けての学習の補助として活用していただけると嬉しいです。
今回は前回に引き続き、資格学校を利用した学習の進め方についてお伝えしていきます。
今回は、後編として製図試験対策についてです。
練習課題への意識
製図試験受験者が練習課題を解くうえで、その課題に対する出来不出来が気になることは、よく理解できます。
しかしながら、皆さんがご承知の通り、資格学校での練習課題の成績が試験の結果となるわけではないため、練習課題の出来不出来”だけ”で一喜一憂するのは、間違っています。
それよりも、内容を精査し、過去に学習した部分ができていなければ、正しく落ち込む必要がありますし、初見の課題である程度できていれば、正しく鼻を高くすれば良いと思います。
以前の記事「《一級建築士製図試験》合格のために本試験と資格学校の違いを知る」でもお伝えしている通り、資格学校の課題には、課題毎に理解してほしいポイントが設定されています。
練習課題の解答内容の精査は、このポイントが理解できたか、また、法規制や空間構成等基本的な試験の根幹となる部分を間違えなかったか等を中心に確認する必要があります。
そして、課題毎に内容の精査を積み重ねるとともに日々の積上げを行って、それを組合わせることで、本試験の課題を完成させていきます。
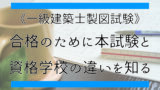
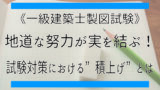
情報収集の方法
製図試験は、決まった答えがない特性上、多くの問題を解き、多くの考え方を知りたいと思うことは自然なことだと思っています。
しかしながら、私個人としては、資格学校を利用している方が、それ以外の方法にも手を出すことは、個人的には反対しています。
以前の記事「《建築士試験》勉強方法を迷っているあなたへ!『資格学校のメリット』」でもお伝えしている通り、資格学校の課題やそれに伴う情報は、常に資格学校から受講者への一方通行で伝達されます。
そして、その情報の処理は、受講者自身に任せられています。
そのため、課題毎に与えられた情報を理解して次の課題に進まなければ、情報を正しく得られず、支払った金額に見合った効果が出ないことが往々にしてあります。
また、その状態で、資格学校以外の練習課題に手を出してしまうと、情報を処理しきれず、ただただ時間だけを浪費して試験に臨むことになります。
「頑張って勉強したのに受からなかった」と言っている受験者の中にこのような方が少なからずいるのは事実です。
そのようにならないためは、資格学校の課題や講師を信じて、資格学校で決められた課題の内容を完璧に理解することが、最も単純で重要であると思います。
学科試験試験 - 資格学校から与えられたものだけでは、合格が難しい
製図試験対策 - 資格学校から与えられたものを完璧にできれば、合格できる