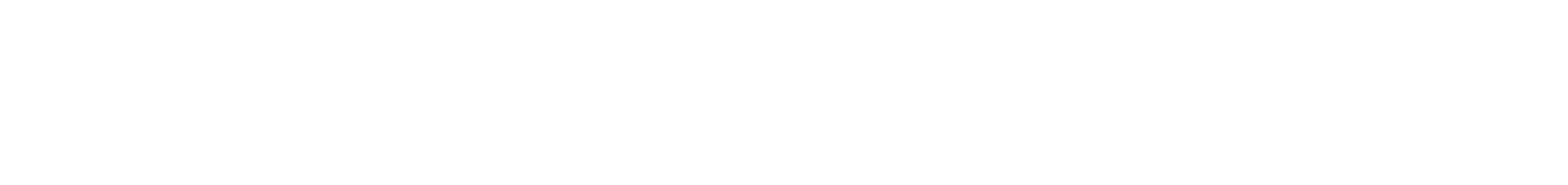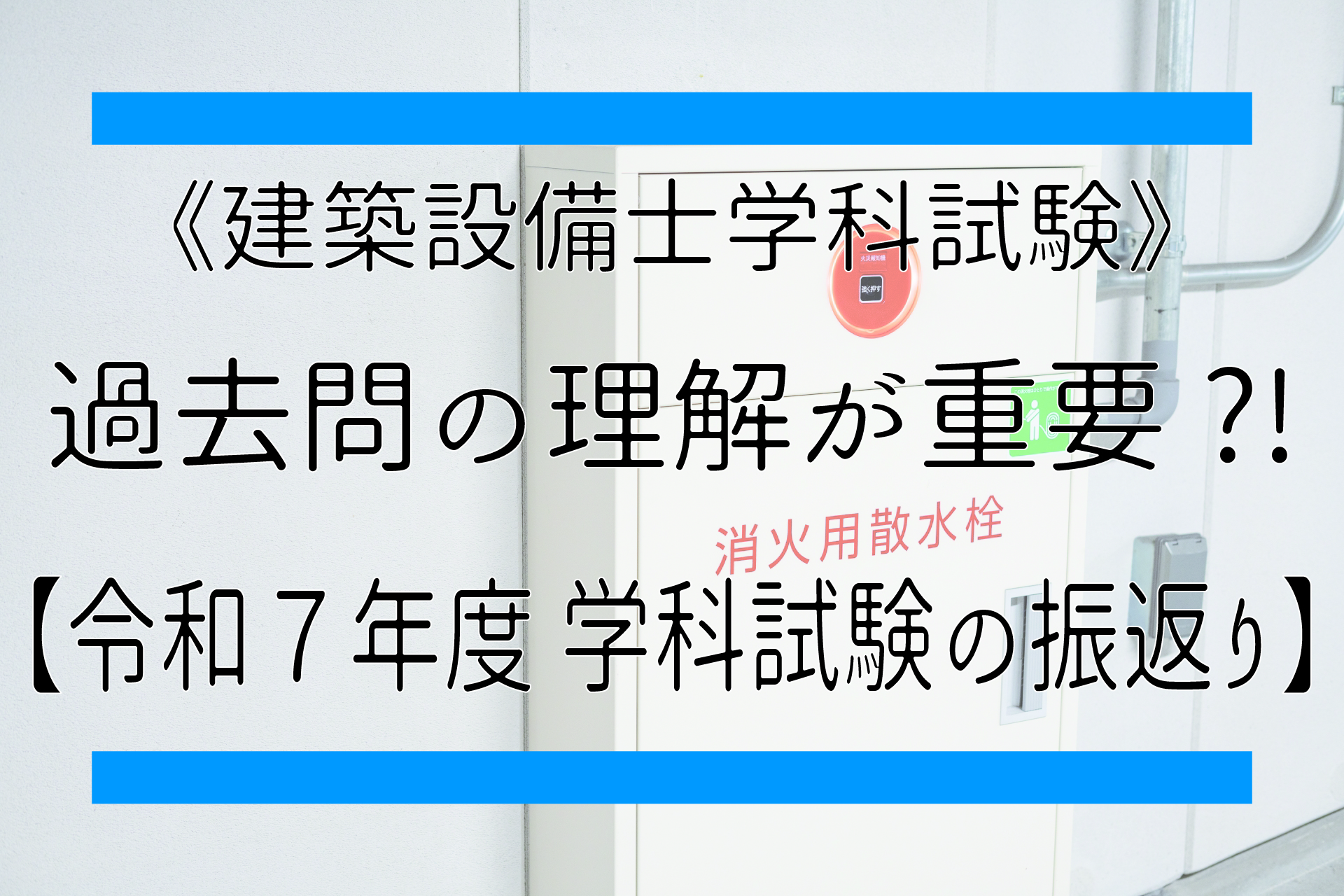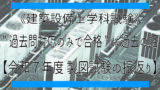建築技術研究所 です。
特に、一級建築士製図試験のポイントや考え方について自身の受験経験を基に記事を作成しています。
試験に向けての学習の補助として活用していただけると嬉しいです。
今回は、受験した建築設備士学科試験の振返りを通じて、これから受験される方の準備に役立てていただきたいと思い、記事にしました。
- “過去問だけ”では、対応できなくなってきている
- 過去問は、出題傾向が変わった令和2年以降のものまでで良い
- 法令集の準備を確実に行えば、点数を伸ばすことができる
建築設備士とは
まず初めに、建築設備士とは、建築士法に基づく国家資格であり、建築士の求めに対し、設計・工事監理のアドバイスを行える資格であり、2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計・工事監理を行う場合、関与が努力義務となっています。
民間工事のみを扱っている設計事務所、設備施工会社の方の中には、あまり意味がないと感じる方もいますが、公共工事の設計等には、建築設備士の配置が特記仕様書で義務化されている場合があり、何より、対外的に設備設計の知識の担保になります。
受験の動機
私が建築設備士を受験した理由は、設備設計一級建築士の受講科目免除を受けるためでした。
設備設計一級建築士を取得するには、建築設備・法適合確認の受講科目があり、合計3日の講習参加とその後に行われる修了考査の受験が必要になります。
一級建築士かつ建築設備士の場合は、そのうちの建築設備の講習2日及び修了考査が免除され、法適合確認の講習1日及び修了考査のみになります。
また、近年の修了者の傾向を見ると、修了者の6割弱が建築設備士を持っています。
学習期間
建築設備士学科試験の学習期間は、半年~3ヶ月程度が一般的のようです。
しかしながら、私の場合は、建築設備士試験の全体像が見えていなかったため、前年の試験よりも前から1年以上の期間をかけて勉強し、学習の時期ごとに使用する教材を変えていました。(次項参照)
合格には、各自の実力や経験に合わせた学習期間を設定することが必要です。
使用教材
私が、学科試験の学習のために使用した教材は、以下の通りです。
詳細は後述しますが、私の場合は、本格的な学習期間は、総合資格学院のテキスト・問題集を使用しました。
- 建築設備士必携テキスト: 試験によく出る重要項目を厳選収録 要点まとめ&問題演習で合格力アップ、おしゃもじ(建築設備チャンネル)
- 建築設備士 学科試験 問題解説、総合資格学院
- 総合資格学院 学科テキスト・問題集、総合資格学院
学習方法
学科試験の学習方法は、前項に挙げたテキスト等をタイミングに合わせて使い分けました。
一般的に複数のテキストを使うよりもひとつのテキストを覚えるくらいに学習した方が効果があるとされていますが、自身の理解度に合わせて組合わせることも必要です。
§1 学習初期①
学習初期は、試験の全体像を掴めていなかったため、「建築設備士必携テキスト」(前項1.)を読み込み、出題傾向の全体像を掴むよう努めました。
「建築設備士必携テキスト」は、学科試験で出題頻度が高い内容を中心にまとめられているため、全体像を掴むのに有効でした。
§2 学習初期②
全体像が大まかに見えた段階で、アウトプットの学習にも着手し、市販の過去問解説「建築設備士 学科試験 問題解説」(前項2.)で過去5年分を3周程度、繰り返して学習しました。
なお、学習初期は法令集の改定前のため、「法規」の学習は行わず、「建築一般」「建築設備」の学習を進めました。
§3 学習中期
学科試験の5か月程度前からは、製図試験を見据えて、総合資格学院の製図対策講座と学科のテキストがセットになったものに申し込み、総合資格の問題集の解説を使って学習しました。(1周め)
総合資格の講座は、高価なことがデメリットですが、以下のメリットがあります。
- 過去問が10年分である。(市販品の倍)
- 項目毎にまとめられ、類似問題が並ぶため出題傾向を掴みやすい(市販品は年度毎)
(総合資格のテキスト・問題集を使用した感想は、次項にて後述します。)
また、法令集の改訂版発売後は、すぐに購入し、インデックス及びアンダーライン引きを行いました。
インデックスは、法令集付属のものを使用せず、「建築設備士必携テキスト」(前項1.)を参考に出題頻度が高い箇所にインデックス及びアンダーラインを引きました。
§4 学習後期
§3の過去問解答の正答率により理解度を測り、理解度が低く、出題頻度が多い問題から2・3周めの学習を進めました。
また、得点しやすい(≒落とすと致命傷になりやすい)数値関係は、特に繰り返して確認し、試験に臨みました。
試験準備~受験の感想
私の認識では、建築設備士の学科試験は、建築士の学科試験と比べて、過去問の比重が多いように思っていたため、過去問の頻出内容を中心に学習を進めましたが、実際の試験では、新出の選択肢も多く、過去問の対応だけでは、合格しにくくなっていると感じました。
また、総合資格の講座用問題集は、当初、過去10年分の課題が収録されていて良いのではと考えていましたが、令和2年の試験制度改定を境に出題内容が変化しているため、令和元年以前の過去問の学習は必須ではなく、過去5年分を確実に学習することができれば、学習効率から考えても必要ではなかったと感じました。
そして、法規の解答には、法令集の準備が欠かせないと改めて感じました。
私が受験した名古屋では、買った時に付いている帯がそのまま付いた法令集を使用している受験者や10年前の法令集を使用している受験者がいましたが、そのような受験者は必ず不合格になっています。
特に令和7年度の学科試験は、法規の基準点(所謂、足切り点)が1点下がる難易度だったとされていますが、前述の準備さえしておけば、周りの評価ほどは難しく感じませんでした。