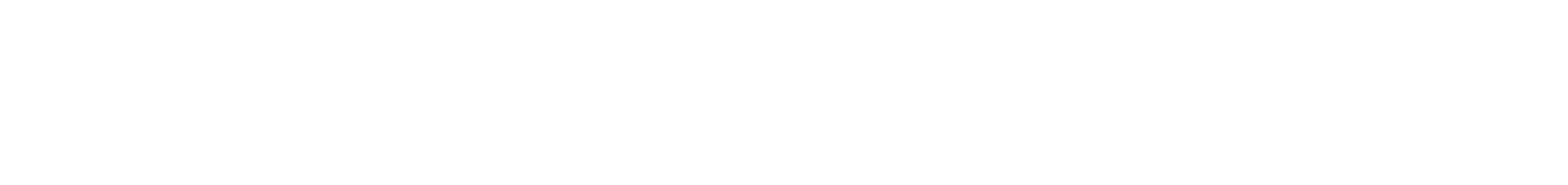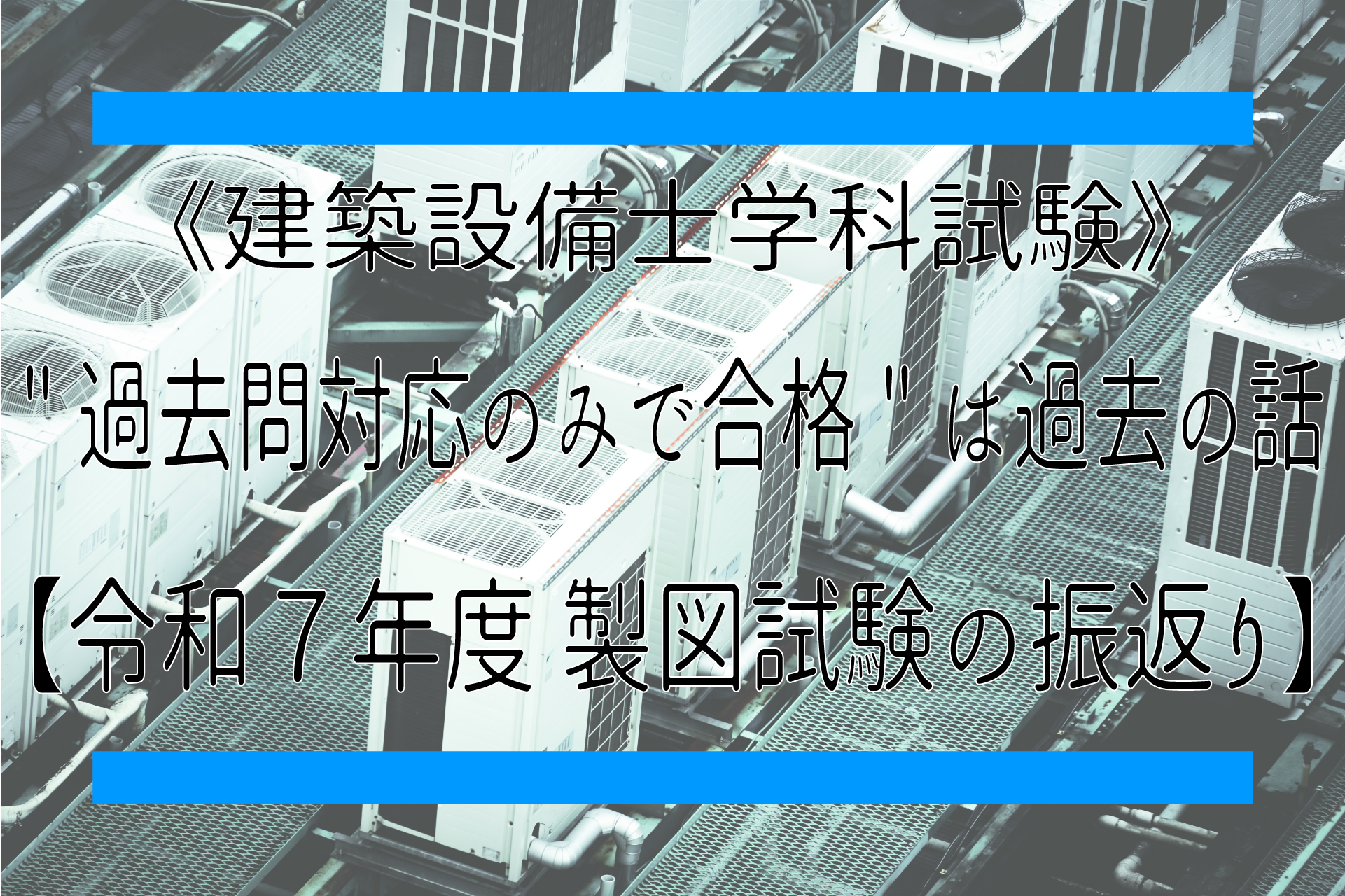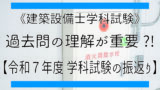建築技術研究所 です。
特に、一級建築士製図試験のポイントや考え方について自身の受験経験を基に記事を作成しています。
試験に向けての学習の補助として活用していただけると嬉しいです。
今回は、受験した建築設備士製図試験の振返りを通じて、これから受験される方の準備に役立てていただきたいと思い、記事にしました。
- 総合資格の選択: 実務経験の不足を補うため、給付金を活用し、近年の発展問題に対応できるカリキュラムを選んだ
- 分野別学習: 必須問題は暗記に頼らず応用力を、機器表は全問正解を目指した過去問の反復練習
- 本試験雑感: 必須問題では全問を埋めること、機器表ではケアレスミスを防ぐための複数回チェック(時間確保)が重要
- 資格学校の評価: 建築士に比べ割高であるが、その効果があったかは、結果論で「YES!」
学習方法は総合資格
建築設備士製図試験に向けての学習方法は、私にとって実質的に総合資格一択でした。
一般的な試験対策としては、日本設備設計事務所協会主催の講習会に参加される方が多いかと思います。しかし、実質的な設備の実務経験が少ない私にとって、この講習会だけでは知識が不十分でした。
そこで、より体系的に学べる資格学校の講座での学習を選択しました。総合資格は、日建学院が過去問中心の構成であるのに対し、近年の発展的な出題傾向にも対応したカリキュラムを組んでおり、実務経験が少ない私にとっては、応用力をつける上で大きな強みでした。これが、総合資格を選択した主な理由です。
また、総合資格の設備士講座はすべて映像授業で、WEB受講も可能でしたが、教育訓練給付金を受給するために通学を選択しました。
この給付金制度は、労働者のスキルアップや再就職を支援するため、厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合に、受講費用の一部が支給されるというものです。
詳細は、下記のリンクをご参照ください。なお、利用については、個人の責任によります。
厚生労働省:教育訓練給付制度について
分野別 重点学習とそのポイント
製図試験は、「必須問題」「選択問題(機器表の計算問題、系統図)」「共通問題(平面図)」に分けて、それぞれの出題特性に応じた対策を繰り返し行いました。
必須問題(記述)の対策
過去問と総合資格の予想問題の二種類を教材として学習しました。近年は発展的な問題として出題されることがあり、過去問の丸暗記だけでは対応が危険だと感じます。出題意図を深く理解し、応用できる力を養うことが重要です。
機器表 計算問題の対策
これは過去問の繰り返し練習が最も効果的でした。出題パターンが決まっているため、繰り返し練習することで計算の流れを掴むことができます。この問題は、1問間違えると、繋がりがある問題すべてに影響するため、全問正解を目指す高い意識を持つ必要がありました。
系統図の対策
上水、下水、雑用水、消火の各系統について、条件ごとの書き分けを練習しました。具体的には、上水における高置水槽パターンと受水槽パターンの違い、下水における重力排水とポンプによる排水の違いなどを重点的に練習しました。
共通問題(平面図)の対策
出題パターンはほぼ同じですが、室のレイアウトにより計画が大きく変わるため、さまざまなパターンで練習を積みました。空調方式については、実務ではコスト面で有利なダイレクトリターンが多いものの、試験的にはリバースリターンの方が出題されやすい傾向があるため(R7年度も出題あり)、特に注意して対策しました。計画時には、梁の位置など建築的な要素やペリメーターゾーンを常に意識して計画を進めることが重要でした。
本試験の感触と対応
必須問題では、1問目から難しい問題が出題され、慌てそうになりましたが、分かる問題から進め、最終的には分からない箇所も含めて全問を埋める対応を取りました。
また、近年は、過去問を発展させた出題が多くなっており、出題への対応として、過去問の解答を丸暗記するのではなく、その内容を理論的に整理しておくことが、重要だと感じました。
R7年度は、初出題の問題が多い印象でしたが、その内容の多くで、総合資格の予想が当たっていたため、焦らずに対応できました。
機器表の計算問題においては、桁の間違いなどのケアレスミスが命取りになると感じました。
これに対しては、全体をひと通り解答した後でも複数回確認できる時間的な余裕があったため、落ち着いてチェック作業を行いました。
その結果、私自身も最後のチェックでミスを拾い、全問正解に繋げることができました。
系統図は、問題の内容自体は難易度が高くないものの、前節で挙げたような条件の読み取りが非常に重要であると感じました。
そのため、読み落としがないよう、条件を整理しながら慎重に進めるよう対応しました。
総合資格の講座 利用レビュー
まず、価格と内容についてですが、建築士の講習に比べて受講者が少ないため、費用は割高に感じました。
しかし、過去問中心ではない構成のため、近年の出題傾向への対応はしやすく、受講の効果があったかについては、結果論として「YES」であった。
特に、必須問題の予想はかなり当たっており、講座で扱った内容を確実に覚えていれば、合格レベルに達すると感じました。
質問対応に関しては、映像講義のみのためメールでの対応でしたが、比較的レスポンス良く回答をもらえました。
添削については、建築士の製図試験とは異なり、明確な正答がある問題が多いため、解答を見れば自己理解できるという意味では、重要度はそれほど高くないと感じました。
建築士の講座の場合、資格学校に通うメリットは、他の受講者の学習進捗が共有され、どのくらい学習すれば合格レベルに達するかを掴むことができた点にありました。
これに対して、建築設備士の講座はあくまで個人の学習に終始したため、相対的な立ち位置を把握しづらいという課題を感じました。この点は、他の学習方法と比較しても優位性を感じなかったため、今後の改善に期待したいところです。
今回の試験での総合資格の評価は、B-(ちょっと合格は厳しいかもレベル)だったのに対し、実際の結果は合格(A評価)でした。
これは、採点が辛めであったこと、また、建築設備士は資格学校に通う人が多数派ではないため、相対評価の面で差異が生じた可能性が高いと考えています。
まとめ
建築設備士の製図試験は、知識の正確さと、何よりも図面や条件を正確に読み取る力が試される試験だと感じました。
- 総合資格の選択: 実務経験の不足を補うため、給付金を活用し、近年の発展問題に対応できるカリキュラムを選んだ
- 分野別学習: 必須問題は暗記に頼らず応用力を、機器表は全問正解を目指した過去問の反復練習
- 本試験雑感: 必須問題では全問を埋めること、機器表ではケアレスミスを防ぐための複数回チェック(時間確保)が重要
- 資格学校の評価: 建築士に比べ割高であるが、その効果があったかは、結果論で「YES!」